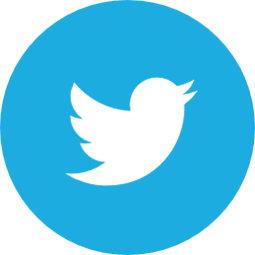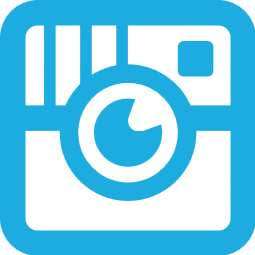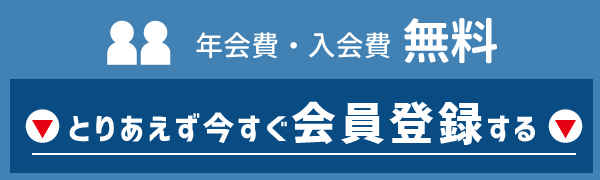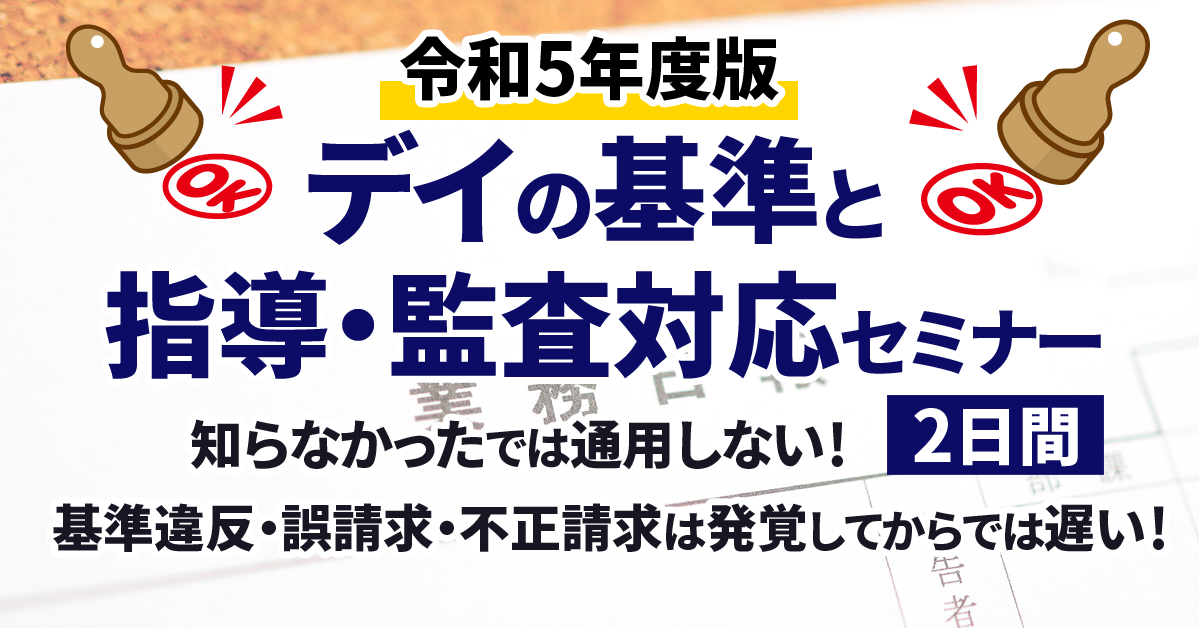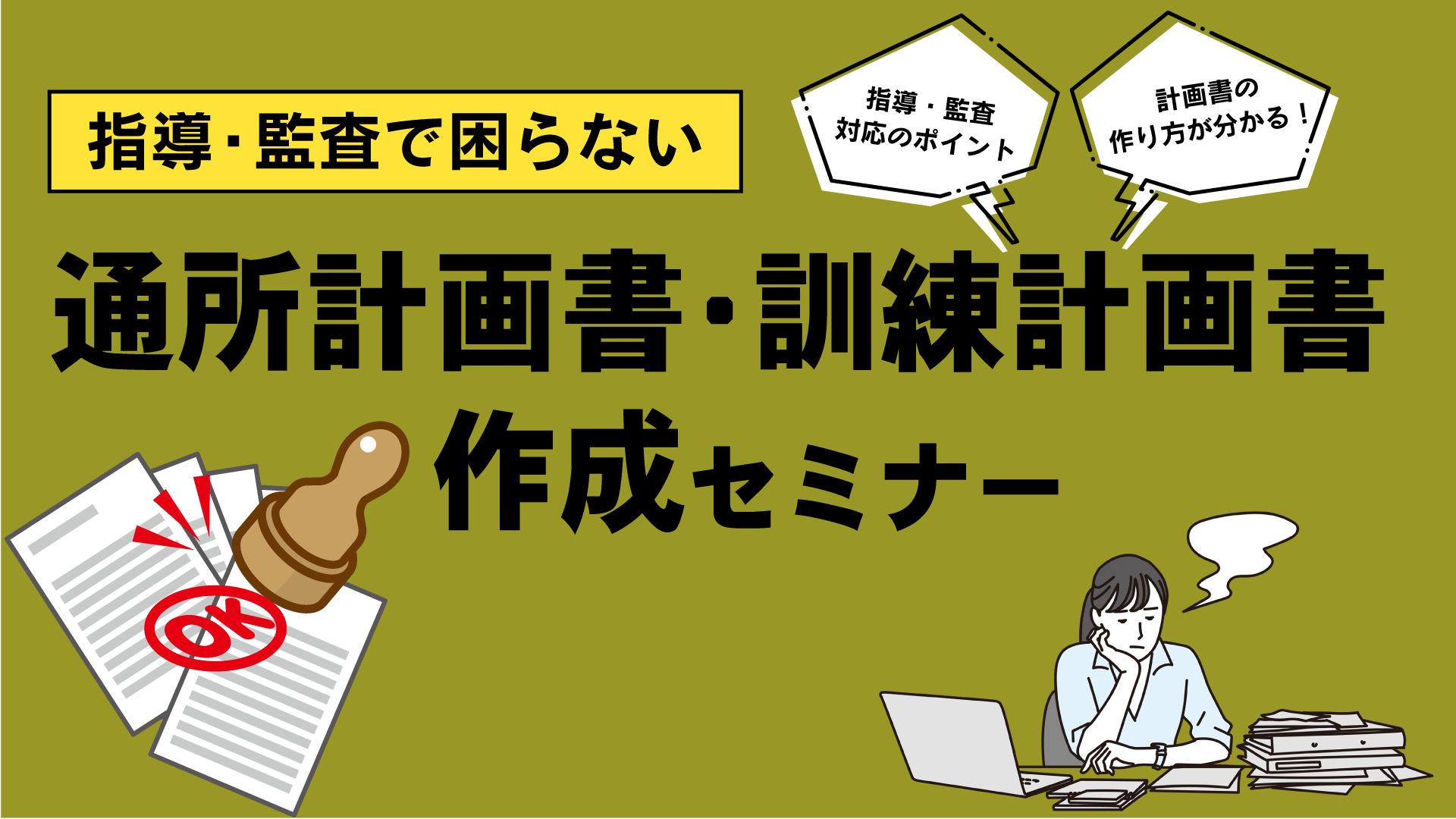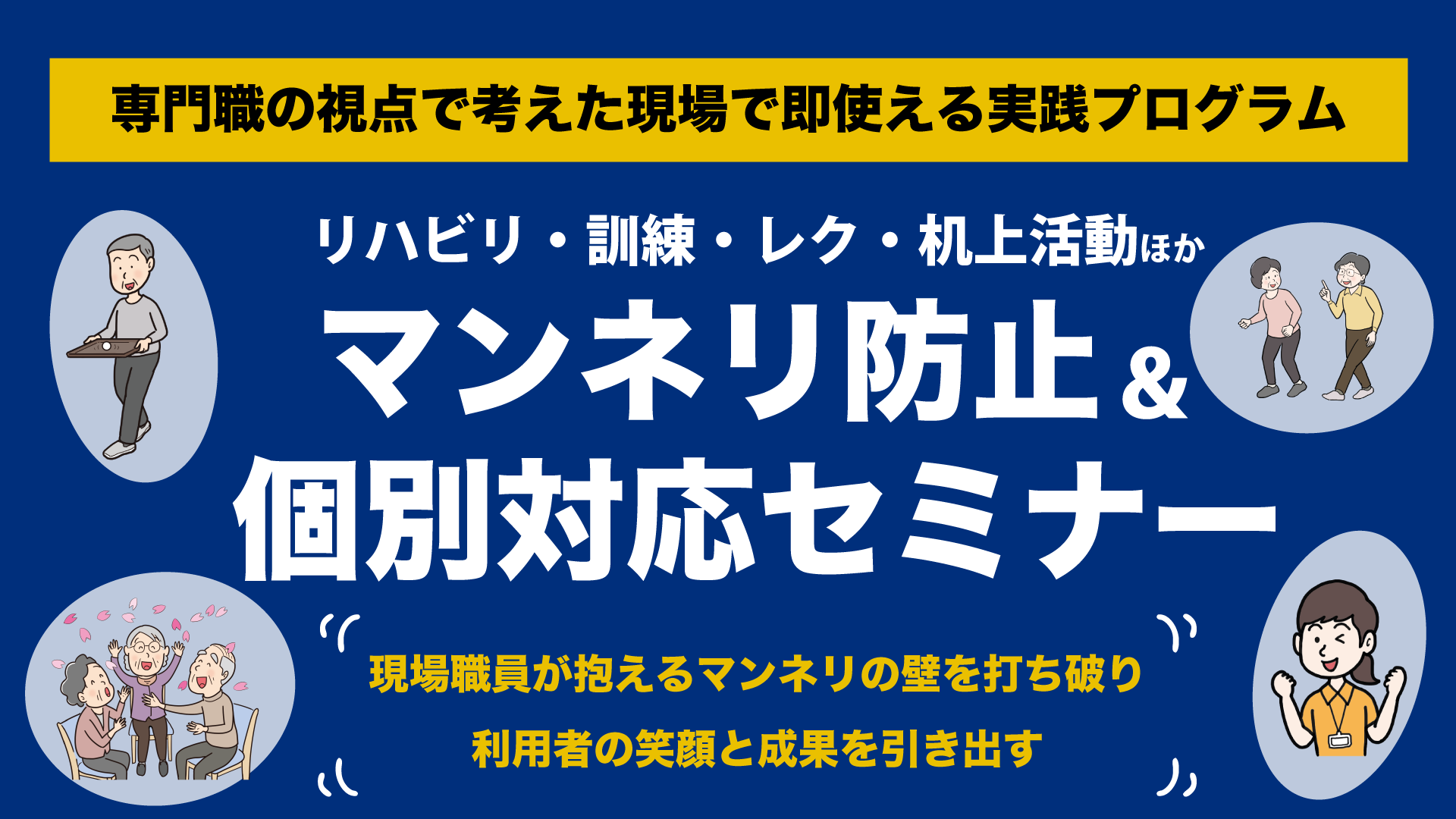高齢化とともに高まる要介護リスク
・年齢が上がるごとに要介護認定を受ける人は増加
[例]
75歳で8人に1人、85歳で2人に1人、90歳では10人中7人が要介護状態
・要介護の主な原因は認知症で、疾患別の第1位
※関節疾患や転倒・骨折も多いが、これらも認知症と関連が深い
「身体の衰え」の裏にある「認知機能の低下」
・要支援段階では「関節疾患」が多く見えるが、実際は認知症の前兆であることが多い
・転倒・骨折の主因も認知症に起因するケースが多く、閉じこもり、衰弱も認知症進行の一部
認知症の発見が遅れる背景
・病院受診率は低く、「おかしいな」と思っても多くの人が1年以上放置
・診断から介護サービス利用開始までにはさらに1年半かかるケースが多く、2年半の空白期間が生まれている
・その間に症状が進行し、家族の身体的・精神的負担も増大している
記憶障害の初期変化と観察ポイント
・アルツハイマー型認知症は認知症全体の約70%を占め、帯状回後部(記憶・見当識を司る部位)が最初に障害されやすい
・初期症状として「出来事の記憶(エピソード記憶)の低下」「日時や場所の見当識の混乱」「言葉の理解や意味の混乱(例:「ペットボトル」→「ペット?ボトル?」)」「計算・読み書きの困難」
専門職が押さえておくべき対応の視点
・「記憶が苦手になった」という訴えがあれば、日時・場所の見当識や言語理解・計算力の確認が重要
・認知症の診断や理解には、医学的知識(脳神経外科・精神医学など)への理解が不可欠
・現場では、表面上の身体的な困りごとの背後に認知機能の変化が潜んでいないかを意識することが重要
【動画】
【情報提供元】
実践!認知症ケア研修会2025
【お役立ち研修】
脳の働きを理解し心の声に寄り添う!実践でひも解く認知症ケアセミナー
https://tsuusho.com/dementia_explained