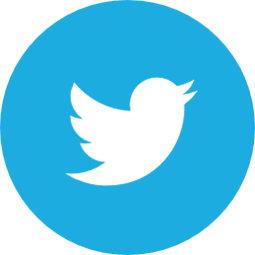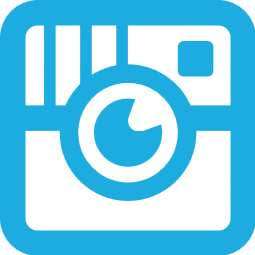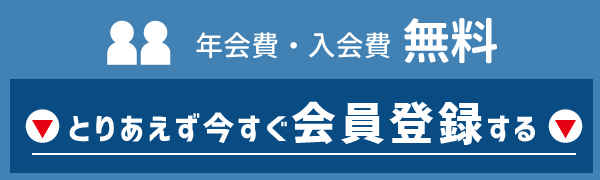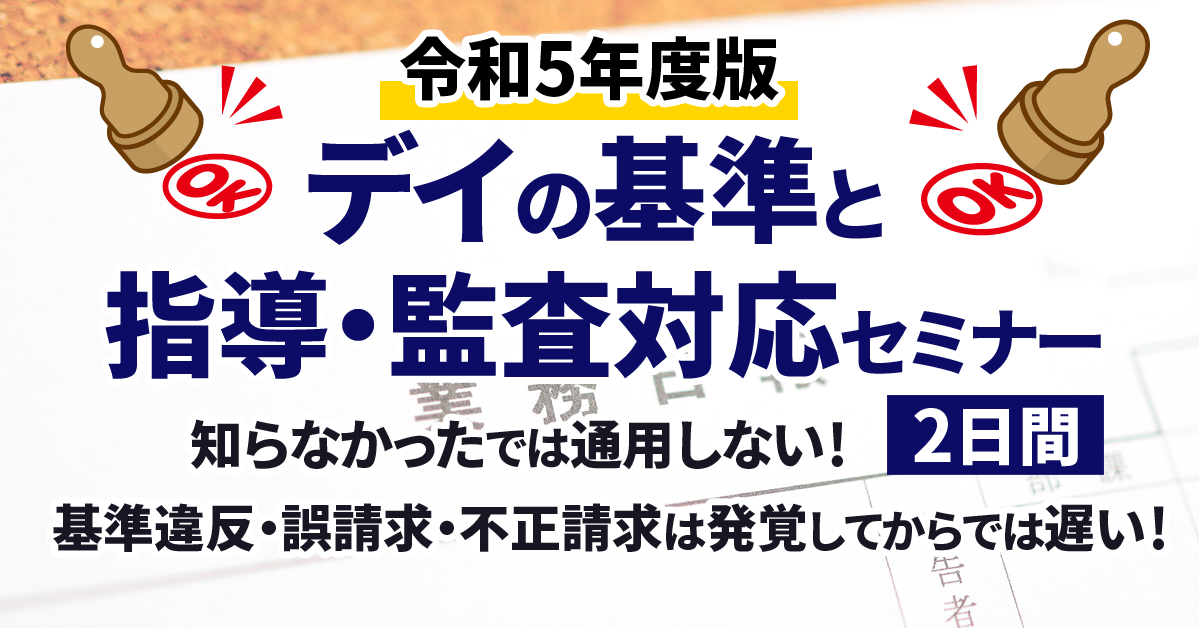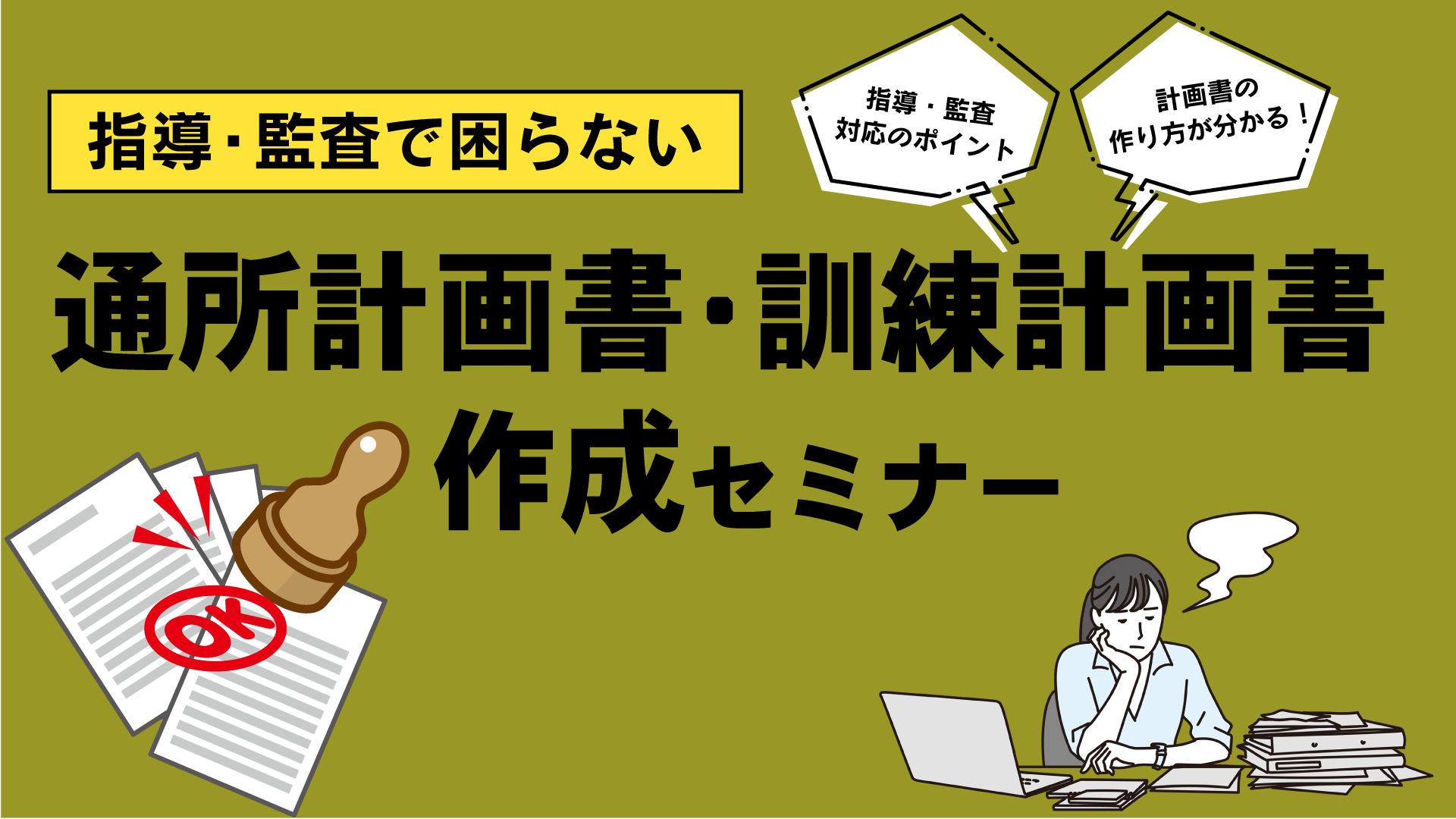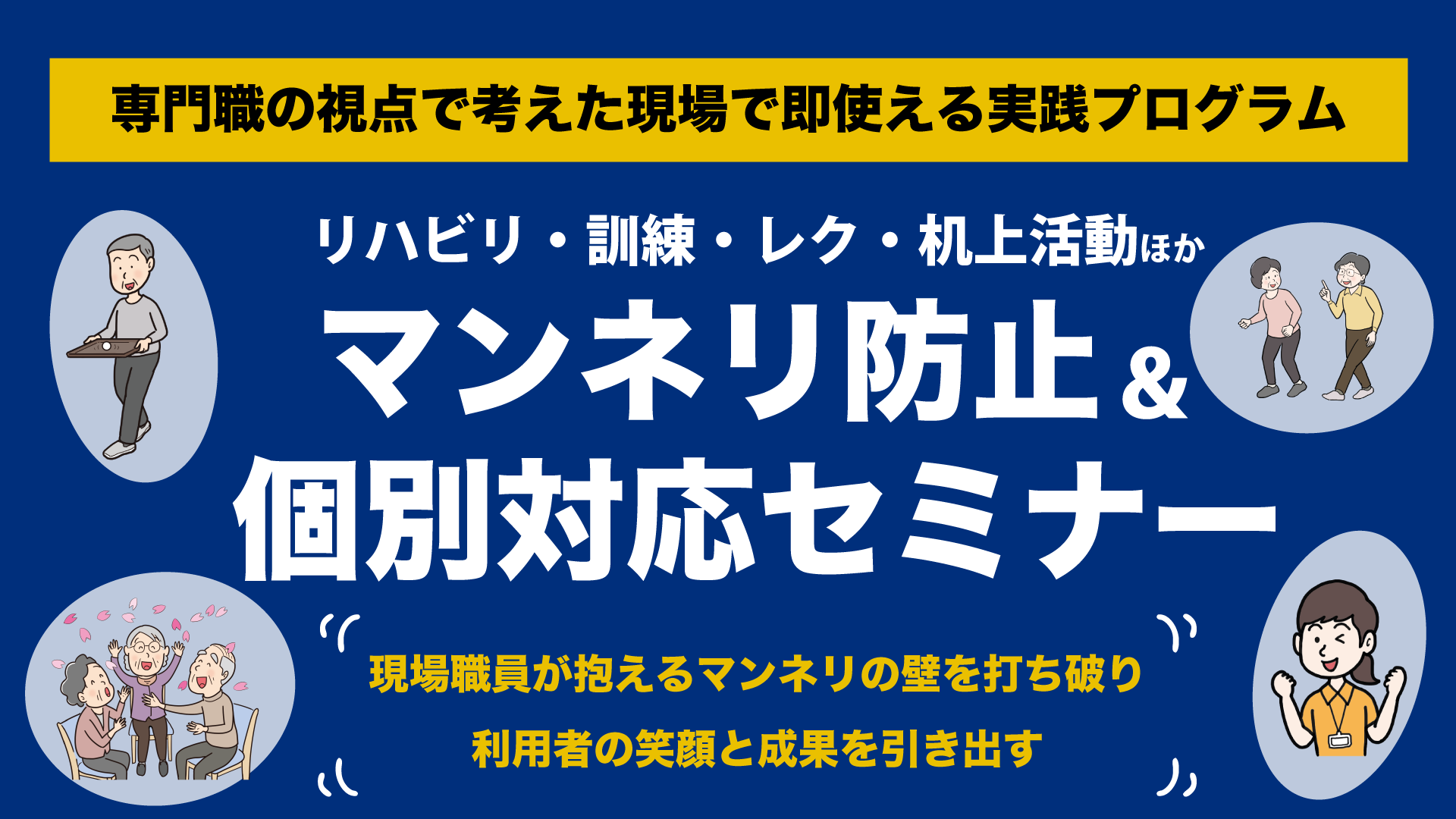日常でできる便秘への対応方法
便秘はその発生機序から「機能性便秘」と「器質性便秘」に大別されます。
機能性便秘はさらに慢性便秘の種類として「弛緩性便秘」、「痙攣性便秘」、「直腸性便秘」、「その他」に分けられます。
弛緩性便秘
[腸の状態]
結腸が弛緩し、蠕動運動が減弱して便を押し出せない状態。
[主な鑑別方法]
・硬く太い便が出る。
・便意を感じにくく、腹痛は少ないがおなかが張る。
[対策・ケア]
炭酸飲料やコーヒーなどを飲んで腸の動きを刺激する。
痙攣性便秘
[腸の状態]
大腸の蠕動運動が強くなり、便の通過が妨げられている状態。
[主な鑑別方法]
・便秘と下痢が交互に起こりやすい。
・便の量が少なく兎糞状の硬いコロコロした便が出る。
・残便感がある。
[対策・ケア]
・温かい牛乳やココアを飲む。
・ホットパックなどで暖める。
直腸性便秘
[腸の状態]
便意を我慢したり浣腸を多用していると直腸・結腸の反射が低下し、便意が起こらない状態。
[主な鑑別方法]
・便意を感じにくくなり、やっと排便しても非常に硬い便が出る。
・排便時に痛みを伴う場合がある。
・おなかが張る。
[対策・ケア]
毎日決まった時間にトイレへ行く習慣をつけ、排泄のリズムを整える。
排泄を促す工夫
排便を促すものは人によってさまざまです。
それらを見つけ出して活用します。
排便を促すポイント(トリガーポイント)を刺激します。
柔らかい紙などで肛門付近を「軽くマッサージする」「内股をなでる、背中をさする」「(トイレに座って)水の流れる音を聞かせる」「ウォシュレットを使用して、肛門を刺激する」など人によってさまざまです。
また「コーヒーを飲む」「冷たい水を飲む」「新しい本の匂いをかぐ」、喫煙される方は「タバコを吸ってリラックスする」など、その人の排泄を促進するものを見つけて活用します。
トイレットペーパーの工夫
トイレットペーパーもペーパーホルダーも白いので、認知症の方などが認識しにくい場合があります。
ホルダーの上部カバーの縁に赤いテープを貼ると認識しやすくなります。
認知症の方など、トイレットペーパーをトイレに捨ててよいかわからない方もおられます。
その場合、トイレの中にごみ箱とわかるものを設置するとよいでしょう。
トイレットペーパーの出し方(折りたたむ、手に巻く、くしゃくしゃに持つ)も人それぞれです。
その人のやり方を尊重した介助を行いましょう。
肛門周辺がただれている方などは、ペーパーをくしゃくしゃにするとより柔らかくなり、肛門への刺激が少なくなります。
【情報提供元】