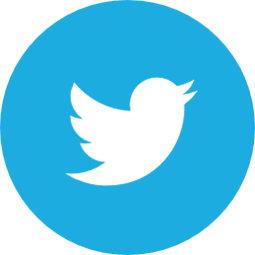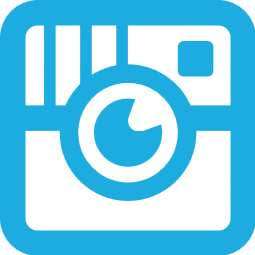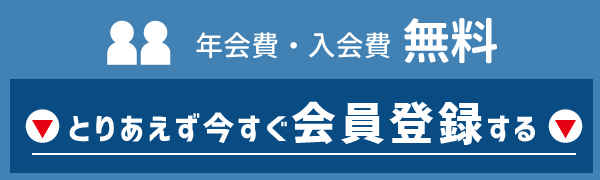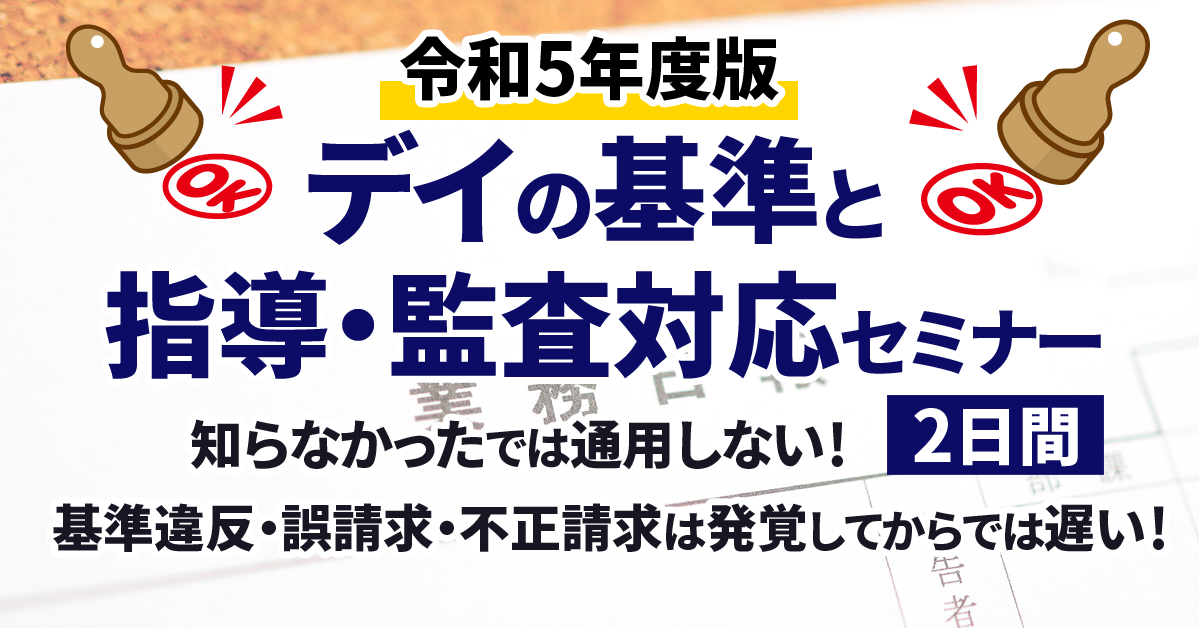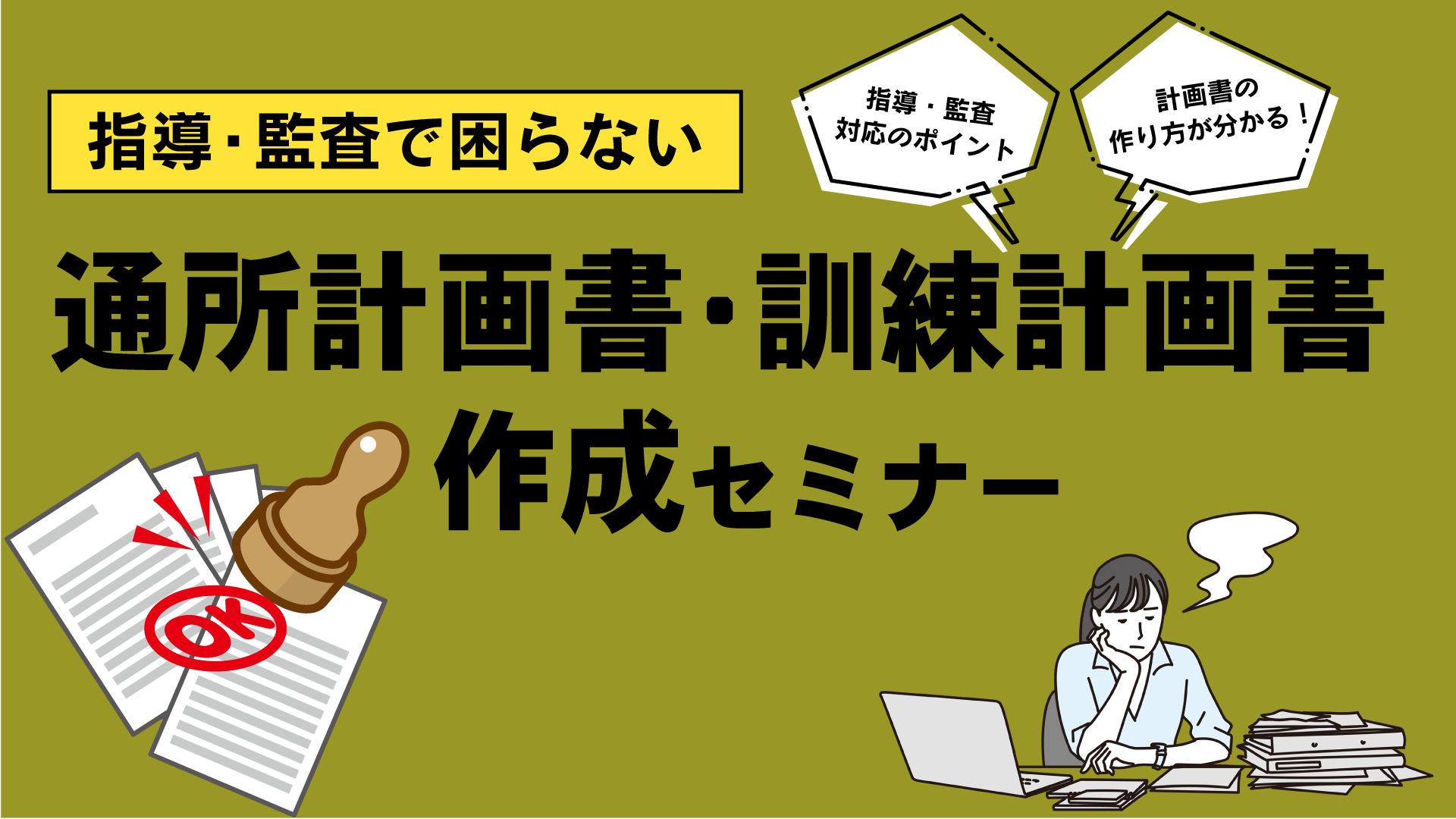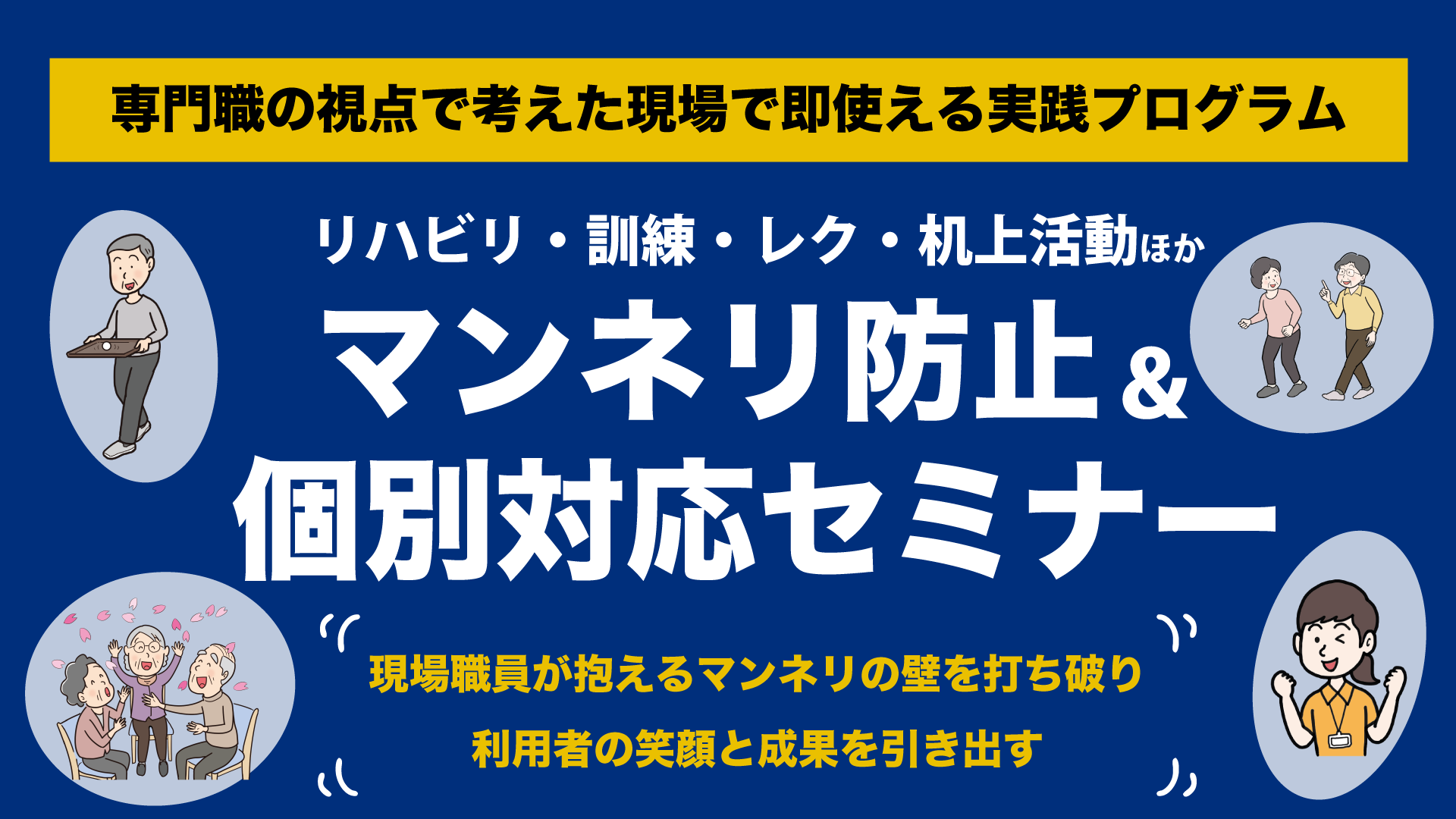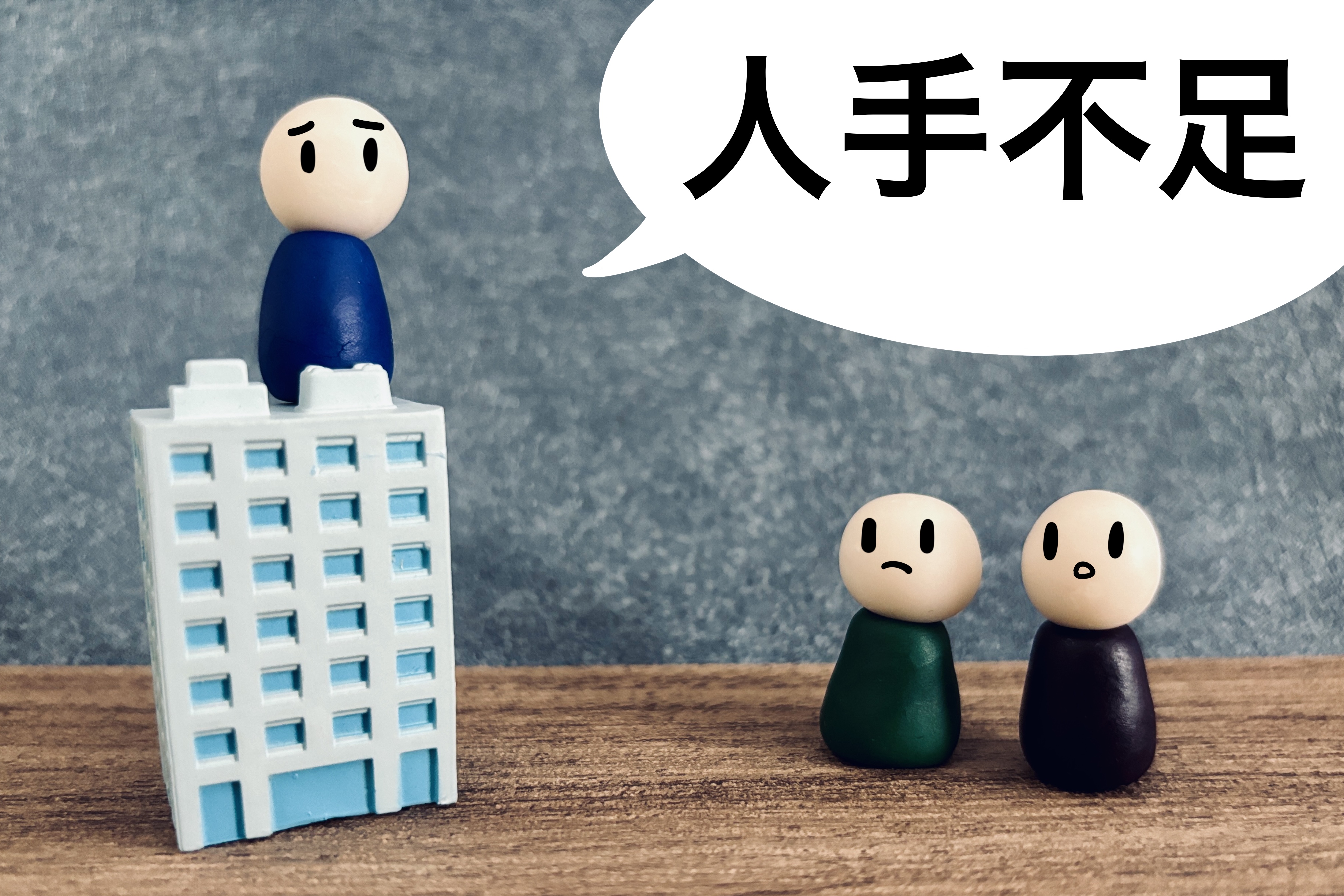
2025年7月7日、東京商工リサーチが発表した最新の調査結果によると訪問介護が大きく揺れています。
今年1月から6月までの訪問介護事業所の倒産件数が45件となっており、上半期としては過去最多を更新したのです。
前年2024年の年間倒産件数は84件でしたが、今年は半年でその半数以上に達しており、このままでは年間100件を超えるペースで推移する可能性が高まっています。
この数字が意味するのは、単なる倒産件数の増加ではありません。
日本の高齢社会を支える在宅ケアの「土台」が、静かに、確実に崩れ始めているという警鐘です。
売上不振が8割超…制度改定が直撃した現場のリアル
東京商工リサーチの調査によると、2025年上半期の訪問介護事業所の倒産理由のうち、約84%(38件)が「売上不振」によるものでした。
介護報酬の減額や利用者数の減少が大きな要因とされています。
2024年度の介護報酬改定では、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。
高齢化が進む中でも、訪問介護の利用者が伸び悩んでいる背景には、以下のような構造的な問題が潜んでいます。
・ヘルパー不足により、受け入れ可能な利用者数が制限される
・サービス提供責任者の配置要件など、制度的なハードルが高い
・働き手の高齢化と新規参入の減少
・都市部と地方でのサービス提供格差
結果として、事業所は提供可能なサービス量を十分に確保できず、「利用者がいるのに受け入れられない」という状況が慢性化しています。
中堅事業者にも倒産の波が…現場の持久力が限界に
今回の発表では、「倒産の波が中堅規模の事業者にも広がっている」という分析もされています。
訪問介護事業所は、個人事業主や小規模法人が中心を占める分野ですが、ここに来てスタッフ20〜30人規模の法人ですら経営破綻に追い込まれるケースが出てきました。
この傾向は、制度改定の影響が単に小規模な「弱い」事業者にとどまらず、構造的な限界が業界全体に及びつつあることを示しています。
「報酬制度の見直し」「記録の厳格化」「処遇改善」など事業所が担う負担が年々増しているにも関わらず、それに見合う収益構造が確保できていないのが実情です。
地方の崩壊がもたらす、全国的な連鎖リスク
特に深刻なのが地方部です。人材確保が困難な地域では、サービス提供そのものがままならず、訪問介護の空白地帯が出始めています。
高齢者の「住み慣れた自宅で暮らし続けたい」という希望を支える訪問介護が消えてしまえば、結果的に次のような連鎖が生まれます。
・地域の高齢者が通所や施設へ流れる
・家族介護の負担が限界に達する
・医療・救急サービスへの過剰依存
・高齢者のQOL(生活の質)の低下
このように、訪問介護の後退は、単なる「一事業者の倒産問題」ではなく、地域包括ケアシステム全体を揺るがす事態に直結しています。
そもそも、なぜ報酬が減るのか?財政と制度のジレンマ
ここで、「なぜ利用ニーズが高まっているのに報酬が下がるのか?」という疑問が湧くでしょう。
実は、日本の介護保険制度は「定められた財源の中でやりくりする仕組み」になっており、総量を抑えるために在宅系サービスにしわ寄せが来やすい構造となっています。
また、厚生労働省は「質の高いサービス提供の推進」や「アウトカム重視」を掲げており、効率性や多職種連携を重視する方向にかじを切っていますが、それが現場にとっては実行困難な理想論になってしまうことも少なくありません。
持続可能な「訪問介護」をどう守るか
このような現状を打破するためには、以下のような包括的な支援が必要と考えることができます。
[1]小規模事業者への緊急的な経営支援
→報酬改定による収益減を一時的にでも補填する制度設計が必要です。
[2]ICTや業務支援ツールの導入支援
→業務効率化によって人手不足を一部補い、現場の負担を軽減します。
[3]ヘルパーの処遇改善とキャリア形成
→単に時給を上げるだけでなく、専門性を評価する報酬制度を整備すべきです。
[4]地域連携の強化
→複数事業所や地域包括支援センター、医療機関との連携で持続可能な体制を構築します。
いま、問われているのは「暮らしを支える仕組み」の再構築
訪問介護は、単なるサービスではありません。
高齢者の尊厳を守り、最期まで「その人らしい暮らし」を支える、地域福祉の要です。
今、業界の崩壊が静かに進んでいるこの状況は、介護業界関係者だけでなく、地域に暮らすすべての人々にとっての課題でもあります。
制度の在り方を、持続可能な「暮らしの支え」に変えていくことが、まさに今、求められているのです。
【情報提供元】
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201549_1527.html
【お役立ち研修】